ローライフレックスといえば二眼レフ、二眼レフといえばローライフレックスである。 こんなことは学校では教わらないが、限りなく常識に近い真実なので知らなかった人は覚えておかれるのがよいだろう。(笑) ローライフレックスと一口に言っても、その歴史は長く、またモデルのバリエーションも様々である。そんな数多あるローライフレックスの中で、ぼくは縁あって「2,8F」と「T」を手に入れることができた。 前者はローライ二眼レフの最高峰ともいうべき完成された最終型である。何十年も前の中古品だが一般庶民がおいそれと買えるような値段では売っていない。これをぼくのようなサラリーマンが買うということは相当な思い入れが必要である。そのあたりは別稿「ローライフレックスとぼく」で述べるとする。 後者は打って変わって、そこそこお手頃な値段で売っているローライフレックスである。当時も、下位機種のローライコードとレンズや部品を共有しながら価格を押さえたいわば廉価版フレックスという位置付けであった。 というわけで、とっても好対照の2台が手元にある。ここではこの2台を比較しながら解説(らしきもの?)を加えていきたいと思う。 | |
 |  |
【 基本スペック 】
撮影レンズ: Carl Zeiss Planar 80mm F2.8 ビューレンズ: Heidosmat 80mm F2.8 シャッター: Deckel Syncro-Compur MXV (B, 1-1/500) 重量: 1,250g バヨネット: III (38mm径) |
【 基本スペック 】
撮影レンズ: Carl Zeiss Tessar 75mm F3.5 ビューレンズ: Heidosmat 75mm F2.8 シャッター: Deckel Syncro-Compur XV (B, 1-1/500) 重量: 1,020g バヨネット: I (28.5mm径) |
【 2,8F のレンズ 】  |
【 T のレンズ 】  |
何と言ってもカメラの一番重要な部分である。
レンズの開放値も違うから大きさも違い、プラナー80mmは堂々としたサイズである。これ以上大きいと不細工になるギリギリのサイズだと思う。(Wローライの顔はコワイ。) ご存知ない方のために付け加えれば、大事な撮影レンズは下の方である。上のレンズは言わばビューファインダーで、大きな実像も見られるしボケを見ながらピントも合わせられる、贅沢なビューファインダーとお考え頂きたい。簡易カメラであるレンジファインダーカメラのファインダーとは志が違うのだ。 またこの2機種は80mmと75mmでちょっぴり画角も違う。2.8Fの方が微妙に望遠。 |
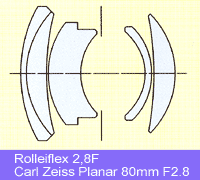 |
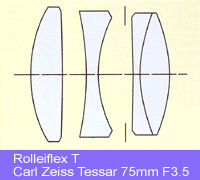 |
さてレンズ構成を比べてみよう。 ぼくは専門家ではないので、こんな図を眺めてもふ〜んてな感じではあるが、とにかく2.8Fのほうが上等そうである。(笑) 対してTのテッサーはシンプルで潔い。(笑) しかしテッサーはこの単純な設計からは想像つかないほどいい写りをする。 2機種の写りはずいぶん趣を異にし、使い分けが楽しい。 |
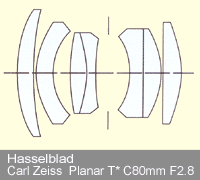 |
左のレンズ構成図は、泣く子もだまるハッセルブラッドの定番レンズ、プラナー T*80mmF2.8である。
昔も今もこの設計であり、現代の35mm判の標準レンズも大体がコピーしたようにこれにそっくりのレンズ構成となっていることからうかがい知れるように、非常に完成されたソツのない設計と言えよう。
しかしお気づきだろうか、同じカール・ツァイスのプラナー80mmF2.8でありながら、ローライ2.8Fのものとはずいぶんと構成が違う。いや、ローライ2.8Fのプラナーが世の定番設計のレンズではないのである。 実際、ローライ2.8Fで撮った写真は、普通の写真とは違うなんともいえない雰囲気をかもし出す。けっして極上のボケをするとか解像度が素晴らしいとかいう話ではなく、「他とは違う」のである。このカメラにしか成し得ないと思われる写真が撮れる(ような気がする)のである。そこらへんがローライフレックス2.8F プラナー80mmF2.8の魅力の要因ではないだろうかと思う。 | |
さあ、それでは次ページにて更なる部分についてぶつぶつ言っていこうと思う。お付き合いいただける方は Next をクリック。
| ||
 |
 |
 |